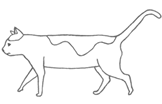プロが教える! 電子申請導入のポイント
第23回
2022年はさまざまな法改正があります。
このタイミングで事前に整理しておきましょう。
- #女性活躍推進法
- #在職老齢年金
- #個人情報保護法
- #社会保険
- #雇用保険
ここがポイント!
- 育児休業法の改正により、男性の育児休業の取得者が増加する可能性が高い
- 社会保険適用拡大により、週約30時間未満で就業しているパート・アルバイトの方は扶養か社会保険加入か判断が必要
- 「えるぼし認定」、「プラチナえるぼし」の認定で企業のイメージUP
社会保険労務士法人アールワンの西嶋です。
2022年度は多くの法改正が行われる年度となっています。
会社としても改正内容の把握と行わなければいけないことを整理しておく必要があります。
今回は法改正のまとめと、会社が行わないといけない点についてお伝えします。
1. 育児・介護休業法の改正
表1
| 法律 | 改正内容 | 施行時期 | |
|---|---|---|---|
| 育児介護休業法の改正 | ① 育児休業等の周知等に関する見直し | 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・取得意向確認の措置の義務付け | 2022年4月1日 |
| 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け | |||
| ② 育児休業の見直し | 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業取得要件の緩和 | ||
| 育児休業の分割取得 | 2022年10月1日 | ||
| 1歳到達後日後の育児休業の見直し | |||
| ③ 出生時の育児休業の創設(男性が対象) | |||
| ④ 1,000人超えの企業に育児休業の取得状況の公表の義務付け | 2023年4月1日 | ||
| 雇用保険法 | 育児休業給付の改正(出生時育児休業給付金の創設) | 2022年10月1日 | |
会社が行わないといけないこと
①~③について
- 就業規則の見直し(事前周知・職場復帰に関する支援、出生時育児休業や育児休業の分割取得、パパ休暇の定め削除など)
⇒ 作成後、就業規則届(変更)を管轄の労働基準監督署へ届出する。 - 育児休業の周知・取得意向について確認する体制整備
⇒ 事前周知用の資料作成(育児・介護休業制度についてまとめたもの)、社内様式の新規作成(出生時育児休業取得申出書など)
労使協定の締結(育児休業の申出を2週間以上~1ヶ月以内とする場合)を行う。
④について
- 公表時期・方法を決める(公表の対象となるのは前年の事業年度の期間となる)
⇒ 公表の方法は会社のホームページ等、一般の方が閲覧・確認できる方法で行う必要がある。
今回の改正は、男性が育児休業を従来よりも取得しやすくなっており、男性の育児休業取得者が増加する可能性が高いです。お客様に改正内容をお伝えして聞こえてくる声は、自分たちの会社で対応しきれるかという不安の声です。しかし、事前に何を行うかを決めて社内体制を整えておけば円滑に対応ができると思っています。
事前準備
① 早い段階(配偶者が出産を迎える4~5ヶ月前)で育児休業の取得希望があるのか確認。
※ 配偶者の出産についてなるべく早めに報告してもらうよう周知。
② 取得希望がある場合、おおよその時期と取得期間を確認。
③ 業務に影響がある場合、取得時期や期間について従業員と相談。(取得時期の変更、繁忙期を避けて分割で取得してもらうなど)
④ 業務の都合上、出社が必要な場合は、臨時で短時間勤務や在宅勤務(テレワーク)を行ってもらうよう相談。
事前準備を行っておけば、急な対応となることがなくなるので落ち着いて対応することが可能となります。また、従業員側にとっても事前に制度や休業中の対応などを予め知っておくことで、安心して育児休業を取得してもらえるようになります。上記について業務フローを作成し、誰が専任で担当するのか予め決めておくのが良いです。
2. 社会保険適用拡大
今回の改正は週約30時間未満で就業しているパート・アルバイトの方が対象となってきます。
表2
| 対象 | 要件 | 現行 | 2022年10月改正 | 2024年10月改正 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所 | 事業所の規模 | 従業員501人以上 | 従業員101人以上 | 従業員51人以上 |
| 短時間労働者 | 労働時間 | 週の所定労働時間20時間以上 | 週の所定労働時間20時間以上 | 週の所定労働時間20時間以上 |
| 賃金 | 88,000円/月額 | 88,000円/月額 | 88,000円/月額 | |
| 勤務期間 | 継続して1年以上の雇用見込み | 継続して2ヶ月を超えての雇用見込み | 継続して2ヶ月を超えての雇用見込み | |
| 適用除外 | 学生ではないこと | 学生ではないこと | 学生ではないこと |
※ 人数要件については、被保険者数でカウントします。
会社が行わないといけないこと
- 新たに適用対象となる社員の確認
⇒ 加入要件を満たす可能性がある社員が誰であるか確認を行う。 - 制度に対する社員説明会若しくは面談の実施
⇒ 社会保険に加入することで、傷病手当金や出産手当金の受給が可能となる点や手取り額のおおよその見込みを伝える。
※ 配偶者の扶養となっている方いる場合、扶養から外れる旨及び影響について周知しましょう。 - 社会保険料の会社負担額の把握
⇒ 会社負担分の社会保険料がどの位になるのか試算し、経営計画に反映させる。
現在、配偶者や家族の扶養の範囲内で仕事をしている方は、健康保険の扶養から抜けて社会保険に加入することになるため、保険料(健康保険、厚生年金)の負担が発生し、収入(手取り)が減少します。
※ 傷病手当金や出産手当金の受給や将来の受給できる年金が増えるメリットはあります。
従業員が気にするのは、加入することで、収入(手取り)がいくらになるのか、これまでの収入を維持するためには、どのような働き方をする必要があるのかなどの確認が必要になります。希望する働き方はそれぞれ異なるため、事前に知っておくことでお互いにどのような働き方(働く日数や時間など)が良いのか相談することができます。結果、働き方の調整などが可能となるので、円滑に進めることができます。
3. 女性活躍推進法の改正
2022年4月1日から従業員101人以上300人以下の中小企業も女性活躍推進法に基づく行動計画の作成・届出が義務化されました。
(従前は100人以下の会社は努力義務)
会社が行わないといけないこと
- 行動計画の作成~届出
自社における女性活躍に関する状況把握・課題分析、課題解決のための目標作成及び社内周知と届出を行う。
※ 自社の状況を確認し、正社員・管理職に占める女性の割合が少ない場合などは、割合を増やすなどの目標を検討する(従業員300人以下の会社が検討する目標は1つでよい)。 - 外部への公表
⇒ 自社のホームページ、女性の活躍推進企業データベースに掲載するなど公表を行う。
少しずつ女性の採用比率を増やす、育児休業をしっかり取得してもらい、復帰に向けたサポートを行うなどから検討すべきかと思います(管理職の割合を増やすなどは、会社によってはハードルが高い目標となる場合がある)。
自社の状況を考慮して無理のない範囲で進めていき、将来的に「えるぼし認定」などの取得を目指していくのが良いでしょう。
女性活躍に関する取り組みの実施状況が優良と認められた場合、「えるぼし認定」、「プラチナえるぼし」の認定を受けることができます。企業イメージがアップしますので、求職者に自社をアピールする絶好の材料となります。
えるぼしの認定を受ける会社に共通して言えることは「従業員の満足度」が高い点です。
満足度が高いと仕事に対する意欲も高くなりますので、業務効率のアップや業績アップに繋がります。
以前から女性の方が多く活躍していると思っていましたが、ますますその場が増えていくので嬉しい気持ちです。
4. その他の改正
- 在職老齢年金の制度見直し(2022年4月改正)
従前の65歳未満の方の在職老齢年金制度は総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「28万円」を超える場合、支給停止若しくは一部支給停止となっておりました。2022年4月以降は「47万円」を超える場合に支給停止若しくは一部支給停止となるよう改正が行われました。
日本年金機構 HP:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html - 個人情報保護法の改正(2022年4月施行)
2020年に改正となった個人情報保護法が、2022年4月から施行されています。
情報漏洩が発生した場合の本人への通知と個人情報保護委員会への通知が義務化、安全管理措置の公表が義務化などのルールが適用になっています。
個人情報保護委員会 HP:https://www.ppc.go.jp/news/kaiseihou_feature/
まとめ
2022年年4月は会社にとって影響のある改正が多く行われており、2022年10月以降も改正が行われるものもあります。
自社が対象なのかを整理して、少しずつでもよいので取り組みを始めましょう。
いろいろな改正があり会社の労務担当者の負担が増すことは事実です。
しかし”自社がより良くなるため”という考えを持ち、取り組むことで、今までよりも良い会社組織を作っていくことができるはずです。
今後も改正などの情報を継続してお伝えしていきます。