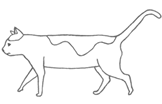プロが教える! 電子申請導入のポイント
第40回
仕事中、通勤中に従業員がケガや病気になった!
労災保険ってなに? 電子申請は可能なのか?
- #労災保険
- #業務災害
- #通勤災害
- #仕事中のケガ病気
- #通勤中のケガ病気
- #健康保険証は使用しない
ここがポイント!
- 労災保険には「業務災害」「通勤災害」がある
- e-Govでほとんどの手続きが申請可能だが、いくつかの理由で紙での申請が大半を占めている
- 令和7年(2025年)1月1日から7つの手続きが電子申請の義務化対象に
社会保険労務士法人アールワンの西嶋です。
仕事中や通勤中に従業員の方がケガをしてしまった場合、健康保険ではなく、労災保険で医療機関を受診します。
その際、労災保険の申請が必要となります。
ですが、労災申請には「業務災害」と「通勤災害」があり、今回はそれぞれの特徴と注意すべき点についてわかりやすくお伝えします。
目次
1. 労災保険の業務災害と通勤災害の違い
まずは、労災保険における「業務災害」と「通勤災害」の違いを押さえておきましょう。
労災保険とは
仕事中や通勤途中の事故で病気やケガをした場合に保険の給付が行われる制度です。
業務災害と通勤災害の違いと注意点
<業務災害>
仕事中のケガや病気が該当します(業務に起因していることが条件)。
例:作業中に指を切ってしまった、会社から取引先に向かう途中、交通事故に遭ったなど。
※ 休憩中のケガ・病気は会社の指揮命令下にないため、業務災害には該当しません。
<通勤災害>
通勤中のケガや病気が該当します(自宅⇔会社の通勤途上で発生していることが条件)。
例:通勤中、駅の階段を踏み外してしまい捻挫した場合や、通勤中、交通事故に遭ったなどが該当します。
※ 仕事の帰りに日用品(食料品、生活雑貨など)の買い物で通勤経路を逸脱した場合、逸脱中のケガなどは通勤災害に該当しませんが、買い物後、通勤経路に戻ってから生じたケガなどは通勤災害に該当します。
こんな時、業務災害・通勤災害に該当する?
① 新入社員が会社の運動会に参加し、ケガをしてしまった場合、業務災害に該当する?
(運動会の参加は任意だが、毎年新入社員は全員参加するのが恒例となっている。)
⇒ 業務災害に該当する。参加は任意でも新入社員の参加が恒例となっている場合、業務扱いとなる。
② 仕事終わりにプライベートの飲み会に参加。帰りの途中に駅の階段で転んでケガをしてしまった場合、通勤災害に該当する?
⇒ 該当しない。合理的な通勤経路を外れてしまった時点からその後は労災と認められない(居酒屋に行くことは私的行為になるため)。
③ 勤務を終えて自宅の最寄駅である横浜駅に着きました。自宅に向かう前にコンビニで夕飯の買い物をしてから帰ることにしました。
買い物を終えて通常の通勤経路に戻り、歩いている途中に車と接触する交通事故に遭いました。この場合、労災に該当する?
⇒ 通勤災害に該当する。通勤経路を逸脱している時は通勤とみなされないが、日常生活に必要な物の買い物の場合、通常の通勤経路に戻った時は通勤とみなされる。
2. 労災申請の流れ
業務災害、通勤災害が発生した場合の流れは以下となります。
1. 労災事故が発生
2. 病院で治療を受ける
※労災で病院を受診する場合は仕事中・通勤中のケガと伝え、健康保険証は利用しない。
3. 会社で申請書を作成し、病院へ提出
労災事故により4日以上会社を休んだ場合
4. 休業(補償)給付申請書を作成し、提出
※死傷病報告書の提出が必要
| 提出書類 | 提出先 | 誰が? |
|---|---|---|
| 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 病院経由で労働基準監督署 | 被災労働者 |
| 療養(補償)給付たる療養の費用の請求書 ※労災指定病院外の医療機関を受診した場合 |
労働基準監督署 | 被災労働者または会社 |
| 療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届 ※医療機関に変更があった場合 |
病院経由で労働基準監督署 | 被災労働者または会社 |
| 休業(補償)給付支給請求書 ※休業4日以上の場合 |
労働基準監督署 | 被災労働者または会社 |
労災関係の書類作成のため、事故の状況や受診した医療機関の確認が必要となります。
労災指定の医療機関で受診した場合は治療費の負担はありませんが、指定外の医療機関で受診した場合、治療費はいったん立て替えてもらい、後日に請求することになります。
※ 労災関係の書類の提出は、原則、被災労働者から行いますが、会社の証明が必要なことや書類の作成が難しいため、会社の労務担当者が作成して、被災労働者に渡すか、会社から提出することが多いです。
3. 業務災害についての注意点
業務災害の場合、以下の点に注意が必要です。
労働者死傷病報告の届出が必要(事業主が対応)
従業員が4日以上休業した場合、都度労働基準監督署に届出が必要です。
※ 休業が4日以上ない場合、四半期ごとにまとめて届出が必要です。
※ 報告書の届出がない場合、「労災隠し」となり、罰則が適用される場合があります。
休業した最初の3日間の休業補償の支払い(事業主の負担)
休業4日目からは、労災保険から休業補償の給付が行われますが、最初の3日間は会社から従業員に対して、平均賃金の60%の休業補償の支払いが必要です。
休業補償は賃金扱いになりませんので、社会保険(健康保険、厚生年金)、雇用保険対象とならず、所得税についても非課税扱いとなります。
※ 通勤災害の場合、会社に責任がないため、上記2点の対応は不要です。
4. 労災申請における電子申請について
労災申請の電子申請について
現状、労災申請(補償、給付)においてe-Govでほとんどの手続きが申請可能になっていますが、紙での申請が大半を占めています。
<理由>
・ 労災指定病院を受診の場合
病院を経由して労働基準監督署に手続き申請を行う必要があります。
医療機関が電子申請をする必要があるのですが、医療機関では申請対応しているところが現状ほとんどないため電子申請が普及しないと考えられます。
※指定病院に変更する際の注意点として、変更前に手続き申請を行っていない場合、病院を経由して労働基準監督署に手続き申請を行う必要があります。
・ 休業補償・給付や療養費用請求の場合
医師の証明や費用の支払いの証明(領収書など)は原本が必要となります。
電子申請後、これらの書類を労働基準監督署に郵送する作業を考えると、紙でまとめて申請するのと変わらないため、電子申請が普及しないと考えられます。
とはいえ、将来的には電子での申請が普及すると思います。
まずは、休業補償・給付、費用請求の手続きから電子申請が普及するでしょう。医師の証明や費用の支払いなどが電子データ化(電子カルテや電子領収書など)、マイナンバー利用拡大などが進めば、電子申請の利用が普及すると考えます。
また、令和7年(2025年)1月1日から、以下の手続きが電子申請の義務化対象となります。
① 労働者死傷病報告
② 定期健康診断結果報告書
③ じん肺健康管理実施状況報告
④ 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
⑤ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
⑥ 有機溶剤等健康診断結果報告書
⑦ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック結果報告)
今後、電子申請での義務化対応となる手続きが増えていきますので、いつでも電子申請ができる環境を整えておくのがよいでしょう。
Charlotte 36plusでは令和7年1月1日から義務化になる手続きの半数が電子申請できます。
社会保険電子申請と一緒にまとめて申請の管理ができるので余分なエクセル管理が不要になります。
https://use-charlotte.jp/charlotte-36plus/
まとめ
業務災害、通勤災害に該当するかどうか、状況を詳細に確認してから労災保険の申請を行いましょう。
電子申請の対応はもう少し先ですが、対応可能となれば労務担当者の負担軽減、役所の審査も早期に完了するでしょう。
新たな情報がありましたら都度、情報共有します。